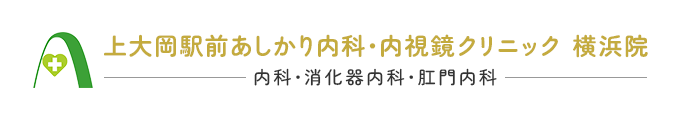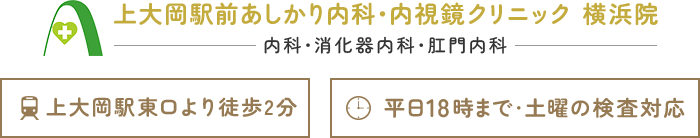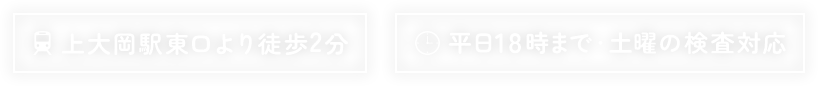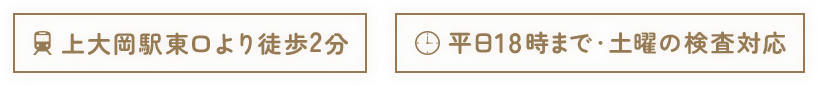脂肪肝とは
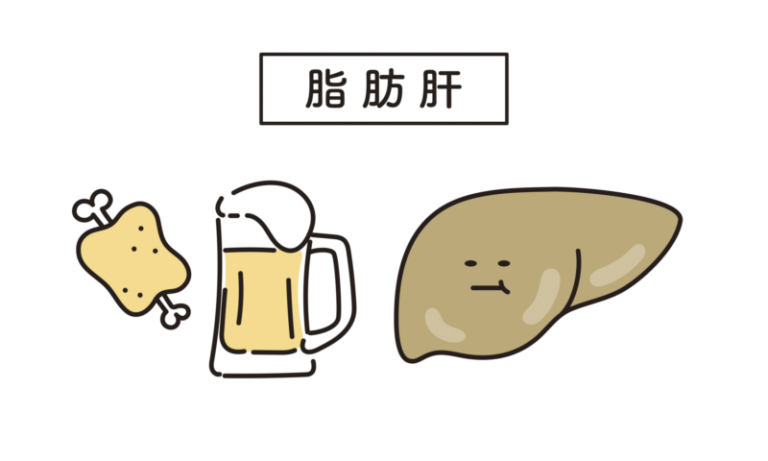 肝臓は使い切れなかった脂肪を中性脂肪やグリコーゲンとして蓄える働きがあります。中性脂肪は、エネルギーの摂取が消費を上回った場合に体内で蓄えられるものであり、その一部が肝臓に蓄積します。肝臓に中性脂肪が蓄積した状態を「脂肪肝」と呼びます。NAFLD/NASH診療ガイドライン2020においては、肝臓を構成する肝細胞の5%以上の細胞の中に脂肪が溜まっている状態を脂肪肝と定義しています。
肝臓は使い切れなかった脂肪を中性脂肪やグリコーゲンとして蓄える働きがあります。中性脂肪は、エネルギーの摂取が消費を上回った場合に体内で蓄えられるものであり、その一部が肝臓に蓄積します。肝臓に中性脂肪が蓄積した状態を「脂肪肝」と呼びます。NAFLD/NASH診療ガイドライン2020においては、肝臓を構成する肝細胞の5%以上の細胞の中に脂肪が溜まっている状態を脂肪肝と定義しています。
脂肪肝の原因は大きくアルコール性と非アルコール性に分類されます。このうち、特に飲酒歴もないのに肝臓に脂肪が貯まってしまう非アルコール性脂肪性肝障害(NAFLD)、代謝異常に関連する脂肪性肝疾患(MASLD)が近年増加傾向にあります。
NAFLDのうち10~20%の頻度で進行性の病態である非アルコール性脂肪肝炎(NASH)に発展します。NASHは年月を経て肝硬変、肝臓がんへと進展する可能性があります。
日本では食生活の欧米化、運動不足などによりNAFLD/NASHの患者さんが増加の一途をたどっており、NAFLDは1000万人以上、NASHは200万人以上と推定されています。
かつてはNAFLD/NASH、肝硬変の診断には肝生検といって肝臓を針で刺して組織を採取する方法が必須でしたが、現在は特殊なエコー(超音波装置)やMRIを用いた非侵襲的な検査である程度の病態を把握することが可能となっています。当院では大学病院と連携しており、これらの特殊な検査を受けることができます。
MASLDはメタボリックシンドロームを基盤病態とし、糖尿病や高血圧、脂質異常症の管理が重要です。MASLDは新しい疾患概念ですが、NAFLDと診断された方の96~98%はMASLDと診断が一致すると報告されています。MASLD、NAFLDおよびNASHは自覚症状がないため、発見が遅れてしまいがちです。健康診断や人間ドックで肝機能異常が指摘され発見される場合もありますが、病態が進行して肝硬変や肝臓がんになってから医療機関を受診されるケースも少なくありません。
健康診断で肝機能異常を指摘されたら放置せず、必ず内科専門医がいる医療機関を受診することをお勧めします。
脂肪肝の症状
脂肪肝は、初期の段階では自覚症状がほとんどありません。
肝臓は他の肝細胞が代わりに機能することができるため、肝臓全体の機能に大きな影響が出るまで症状が現れにくいです。そのため、「沈黙の臓器」と呼ばれています。
しかし、脂肪肝が進行して肝硬変になると、様々な症状が現れることがあります。例えば、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、腹水(腹部に水分が溜まり腫れる)、膨満感、足のむくみなどが現れることがあります。これらの症状が現れると、病気がかなり進行している可能性があります。
脂肪肝の原因
NAFLDは、肝臓が余ったエネルギーを貯蔵する際に中性脂肪に変換し、さらに肥満の人では血糖値を下げるインスリンの効果が低下するため、肝臓で中性脂肪が増加することで引き起こされます。他の原因として、ステロイド剤などの薬の副作用や栄養障害による代謝異常、極端な痩せなども考えられます。最近の研究では、特定の遺伝子(PNPLA3など)の型がNAFLDに関与していることも分かってきています。
脂肪肝の検査
脂肪肝は自覚症状がほとんどないため、血液検査や超音波検査などによって診断されることが多いです。
超音波検査
 超音波検査によって肝臓の状態を確認します。超音波検査では肝臓内部の脂肪の蓄積を可視化することができます。
超音波検査によって肝臓の状態を確認します。超音波検査では肝臓内部の脂肪の蓄積を可視化することができます。
血液検査
 肝機能を確認するために血液検査が行われます。肝臓に障害がある場合、特定の酵素やタンパク質の血中濃度が異常になることがあります。
肝機能を確認するために血液検査が行われます。肝臓に障害がある場合、特定の酵素やタンパク質の血中濃度が異常になることがあります。
このような検査結果から脂肪肝の疑いが指摘されることもあります。
さらに、他の肝臓病の疑いを除外するために追加の検査が行われる場合もあります。CT検査やMRI検査などの画像検査、肝臓の組織を調べる肝生検などが行われることがあります。
脂肪肝の治療
 脂肪肝の治療では、まず生活習慣の改善が求められます。特にメタボリックシンドロームを合併している場合は、肥満、糖尿病、脂質異常症、高血圧などの生活習慣病を改善することが重要です。体重減少を目指し、食事の改善や適度な運動を取り入れた減量を行うことが一般的です。
脂肪肝の治療では、まず生活習慣の改善が求められます。特にメタボリックシンドロームを合併している場合は、肥満、糖尿病、脂質異常症、高血圧などの生活習慣病を改善することが重要です。体重減少を目指し、食事の改善や適度な運動を取り入れた減量を行うことが一般的です。
体重減少だけでは効果が得られない場合、ビタミンCやビタミンEなどの抗酸化作用を持つサプリメントの摂取や、インスリンの効果を改善する糖尿病治療薬の使用が検討されることもあります。また、高血圧や脂質異常症などの基礎疾患がある場合は、それぞれに適した薬物療法も行われます。
なお、アルコールを摂取しない場合でも、非アルコール性脂肪肝(NASH)は放置すると肝硬変や肝がんに進行する可能性があるため、適切な治療が必要です。医師の指示に従い、定期的な検査やフォローアップを受けながら治療を行いましょう。