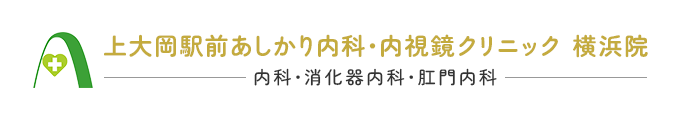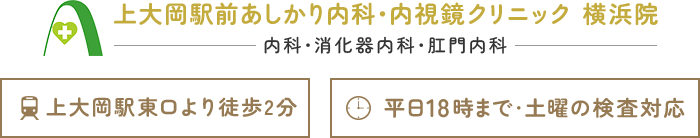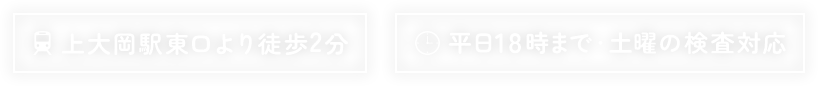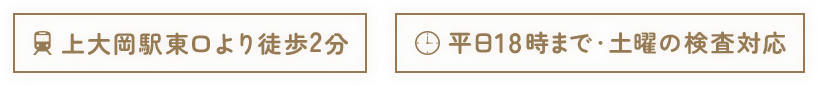以下のような症状で
お悩みの方はご相談下さい
- 水状または泥状の下痢が長期間続く
- 頻繁な下痢で仕事が妨げられる、外出するのをためらってしまう
- 下痢に血が混じる
下痢とは
 下痢は、便中の水分量が増加し、便の形状を保つことができずに液状または泥状のまま排出される状態を指します。
下痢は、便中の水分量が増加し、便の形状を保つことができずに液状または泥状のまま排出される状態を指します。
下痢の原因は様々であり、体の異常や不調の徴候となることもあります。大腸がんなど致命的な疾患が潜んでいることもあるため、下痢は軽視せずに適切に対処する必要があります。下痢が長期間続くと、脱水症状を引き起こしたり、電解質やタンパク質などの必要な栄養素も失ってしまう可能性があります。
下痢の原因
下痢の原因には以下のようなものがあります。
腸管の水分吸収量の減少
(腸管蠕動運動の異常、
機能的な異常)
排泄物である糞便に含まれる水分は小腸や大腸で吸収され、便が形成されます。しかし、腸管内で発生する病気によって、便の排出に関わる蠕動運動が過剰に活性化してしまうことがあります。このような状態では、糞便は通常よりも滞留時間が短くなり、腸管での水分の吸収量が低下します。その結果、便が液状または泥状となり、下痢の症状が現れます。
腸管の炎症
(腸管のむくみ)
腸管に炎症が起こることで、腸管壁の組織に含まれる滲出液(組織液)が腸管内に漏れ出し、便の水分含有量が増加します。その結果、下痢の症状が発生します。
炎症の原因は様々であり、感染症や膠原病、潰瘍性大腸炎などが挙げられます。
ストレス等の心身の不調
腸管の働きは、自律神経系と密接に関連しています。精神的なストレスや過度な緊張状態が続くと、自律神経系のリズムが乱れ、腸の運動や消化機能が影響を受けることがあります。このような状態では、腸管の運動が亢進し、便が急速に腸管を通過するために下痢を発症することがあります。
生活習慣の乱れ
 暴飲暴食やアルコールの過剰摂取など、生活習慣の乱れが下痢の原因となることがあります。体の冷えは胃腸の血流を悪化させ、消化吸収能を低下させ、下痢を引き起こすことがあります。冬などは体を冷やさないように温かく過ごすこと、夏は冷たい飲み物などを一気にたくさん飲まないこと、などが大事です。
暴飲暴食やアルコールの過剰摂取など、生活習慣の乱れが下痢の原因となることがあります。体の冷えは胃腸の血流を悪化させ、消化吸収能を低下させ、下痢を引き起こすことがあります。冬などは体を冷やさないように温かく過ごすこと、夏は冷たい飲み物などを一気にたくさん飲まないこと、などが大事です。
下痢を引き起こす疾患
下痢を引き起こす疾患には以下のようなものがあります。
感染性腸炎
サルモネラ腸炎、カンピロバクター腸炎、腸炎ビブリオ、出血性大腸菌腸炎、ノロウイルス、ロタウイルス、腸管アデノウイルスなど細菌やウイルスによって下痢や嘔吐、腹痛、発熱などの症状を来します。
薬剤性腸炎
一部の抗生物質、抗がん剤(特に免疫チェックポイント阻害薬)、非ステロイド性抗炎症薬、低用量アスピリン、骨粗しょう症治療薬、経口避妊薬、PPI(プロトポンプ阻害薬)の長期間投与などによって下痢が引き起こされる場合があります。この場合、多くは原因薬剤を中止することで改善します。
過敏性腸症候群
過敏性腸症候群とは、大腸に腫瘍や炎症といった病気がないにもかかわらず、腹痛や腹部の張りなどの違和感、便通の異常が数か月以上にわたって続く状態のことをいいます。詳しくは「過敏性腸症候群」のページをご参照ください。
胆汁性下痢
肝臓で生合成される消化酵素のひとつである「胆汁」が排便に大きく関わっていることが近年わかってきました。胆汁は多く分泌され過ぎると下痢を引き起こし、逆に欠乏すると便秘を引き起こすことがわかっています。何らかの原因で大腸内に胆汁が多く排出される方は食後にすぐにトイレに行きたくなったり、1日に何回も下痢がでることがあります。
炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎、クローン病)
炎症性腸疾患とは、免疫機構が異常をきたし、自分の免疫細胞が腸の細胞を攻撃してしまうことで腸に炎症を起こす病気です。慢性的な下痢や血便、腹痛などの症状を伴います。主に潰瘍性大腸炎とクローン病が有名で、ともに比較的若い方に発症しやすい傾向があります。日本は欧米化によって患者数は年々増加傾向にあり、高齢発症するケースも増えています。詳しくは「炎症性腸疾患」のページをご覧ください。
大腸がん、大腸ポリープ
大腸がんは、初期段階でも下痢を引き起こすことがあります。下痢の症状がある場合でも、それがただの下痢であるか、それとも大腸がんが原因であるかは判断が難しい場合もあります。そのため、下痢症状に加えて腹痛や血便などの症状がみられた場合には、特に注意が必要です。
その他の疾患
- 甲状腺機能亢進症
- 腸結核
- Collagenous colitis
- WDHA症候群、Zollinger-Ellison症候群
- 虚血性腸炎
- 小腸の疾患
- 慢性膵炎、膵癌 など
下痢によって
引き起こされる他の症状
下痢による体内の水分減少は脱水症状を引き起こす可能性があります。脱水症状の初期症状としては、口の渇き、皮膚の乾燥、立ちくらみ、低血圧などが現れることがあります。
脱水症状が進行すると、腎臓や心臓などの臓器にも負担がかかり、腎不全や不整脈などの症状を引き起こすことがあります。さらに、下痢によって水分と共にナトリウムやカリウムなどの電解質も体外に排出されてしまいます。電解質のバランスが崩れることで、手や足の力が入らなくなったり、痺れたり、痙攣したりするなどの症状が現れることもあります。
下痢の治療
水分補給、点滴

下痢を繰り返すと、体内の水分が外に出てしまい脱水状態になります。脱水が長引き高度になると、血液が濃縮状態になります。特にご高齢者では元々の動脈硬化性疾患や心疾患などが併存すると、血栓を形成する恐れがあり、脳梗塞や血栓症のリスクがあります。若い方でも油断は禁物で、低カリウム血症を起こしたり、腎機能障害を起こすこともあります。
スポーツドリンクには体内の水分と電解質のバランスを保つための成分が含まれており、脱水症状の予防や改善に効果的です。水分だけでなく、ナトリウム、カリウム、糖分などの栄養素も補給することで、体内の水分吸収や電解質の調節をサポートします。
ただし、脱水症状が深刻な場合は、口からの水分摂取だけでは不十分な場合があります。このような場合には、医師の判断にもとづき点滴を行うこともあります。
薬物療法
 下痢の薬物療法は、原因によって使用される薬剤が異なります。感染症が原因の下痢に対して下痢止めを使用することはかなり危険で、自己判断で市販薬などを使用することは推奨されません。下痢型過敏性腸症候群や胆汁性下痢には効果の高い薬剤があり、適切に選択すれば症状はかなり改善されます。
下痢の薬物療法は、原因によって使用される薬剤が異なります。感染症が原因の下痢に対して下痢止めを使用することはかなり危険で、自己判断で市販薬などを使用することは推奨されません。下痢型過敏性腸症候群や胆汁性下痢には効果の高い薬剤があり、適切に選択すれば症状はかなり改善されます。
下痢が続く場合は、消化器内科専門医を受診し、的確な診断を受けたうえでお薬を処方してもらうとよいでしょう。
生活習慣で気を付ける事
水分補給
下痢の際の水分補給は一度に大量に摂ると吐き気を引き起こすことがありますので、少量ずつ小分けにして水分を摂取してください。また冷やしすぎず、常温で飲むことでお腹を冷やすことなく水分が摂取できます。
睡眠
十分な睡眠をとることも重要です。睡眠不足は体の免疫力を低下させる可能性があり、回復に時間がかかることがありますので、睡眠時間を確保しましょう。
食事
食事も規則正しく摂ることが大切です。消化の良い食材を選び、冷たい物や辛い物などの刺激物はできるだけ避けましょう。食事の量も適度に抑え、暴飲暴食や過度なアルコール摂取は控えるように心がけましょう。
下痢でお悩みの方は
当院にご相談ください
 下痢は軽視されがちな症状ですが、その背後には様々な疾患が潜んでいる可能性があります。実際に、ただの下痢と思っていた方が大腸がんの初期症状であったというケースもあります。些細な症状でも、お困りの際にはお気軽に当院にご相談ください。
下痢は軽視されがちな症状ですが、その背後には様々な疾患が潜んでいる可能性があります。実際に、ただの下痢と思っていた方が大腸がんの初期症状であったというケースもあります。些細な症状でも、お困りの際にはお気軽に当院にご相談ください。