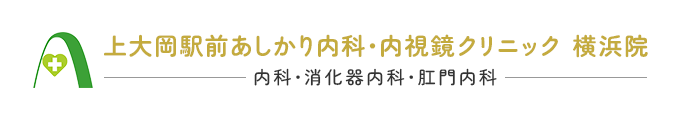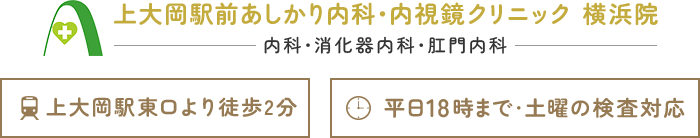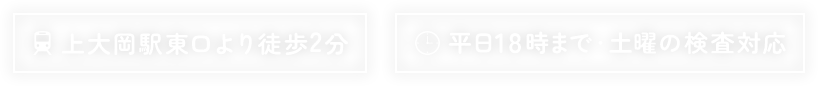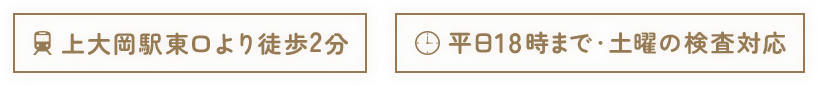高血圧について
 血圧とは、心臓から送り出された血液が血管の内壁を押す力(圧力)を指します。最高血圧は心臓の収縮時に測定され、最低血圧は心臓の拡張時に測定されます。血圧は血液の流れの勢いや血管の柔軟性によって変動します。また、環境や身体の状態によっても変化します。血圧を決定する主な要因として、心臓が1回の拍動で全身に送り出す血液量(心拍出量)や血管のしなやかさ(弾力性)のほか、血液が血管に流れ込む際の末梢血管の抵抗力(血管抵抗)、血液の粘度などが挙げられます。
血圧とは、心臓から送り出された血液が血管の内壁を押す力(圧力)を指します。最高血圧は心臓の収縮時に測定され、最低血圧は心臓の拡張時に測定されます。血圧は血液の流れの勢いや血管の柔軟性によって変動します。また、環境や身体の状態によっても変化します。血圧を決定する主な要因として、心臓が1回の拍動で全身に送り出す血液量(心拍出量)や血管のしなやかさ(弾力性)のほか、血液が血管に流れ込む際の末梢血管の抵抗力(血管抵抗)、血液の粘度などが挙げられます。
持続的に高い血圧が続く状態を高血圧といいます。高血圧が長期間続くと、動脈硬化が進行し、心筋梗塞や脳卒中、脳梗塞の発症リスクが増加します。高血圧と動脈硬化は相互に悪化し合うため、悪循環を引き起こす可能性があります。日本人は高血圧の割合が高く、自覚症状が少ないため、適切な処置や治療が遅れる傾向があります。日本には高血圧の方が4300万人いると推定されており、そのうち自らの高血圧を認識していない方が1400万人、認識しているのに未治療の方が450万人います。高血圧に起因した脳心血管病(心筋梗塞や脳卒中など)死亡者数は年間10万人と言われています。
生活習慣病や重篤な疾患の予防のためには、早い段階から血圧のコントロールが重要です。高血圧が持続する場合は、お早めに当院にご相談ください。
高血圧の原因
過剰な塩分摂取、喫煙、飲酒、肥満、運動不足などの生活習慣の乱れは、高血圧の原因となることがあります。遺伝的要因も高血圧の発症に関与しています。
また、他の疾患や薬の服用も血圧に影響を与えることがあります。
特に、日本人の塩分摂取量が多いことが高血圧の要因として挙げられます。食事に含まれる塩分は血液量を増加させるため、血圧が上昇することがあります。そのため、減塩や塩分摂取の見直しは高血圧の改善に効果的です。
高血圧の主な合併症
| 脳疾患 | 脳出血・くも膜下出血・脳梗塞などの脳血管疾患 |
|---|---|
| 心疾患 | 心筋梗塞・狭心症・心肥大・うっ血性心不全・冠状動脈硬化 |
| 腎疾患 | 腎硬化症・腎不全 |
| 心血管疾患 | 大動脈瘤・閉塞性動脈硬化症 |
血圧の基準値
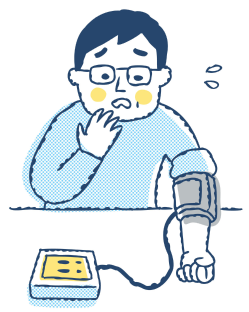 成人における正常血圧は、120/80mmHg未満で、140/90mmHg以上が高血圧とされています。
成人における正常血圧は、120/80mmHg未満で、140/90mmHg以上が高血圧とされています。
また、120~129/80mmHg未満は正常高値血圧、130~139/80~89mmHgは高値血圧とされています。これらの状態は高血圧に進行しやすいとされており、予防が重要です。この段階では、比較的軽度な食事療法や運動療法などの生活習慣の見直しによって血圧を改善させることができる可能性があります。
ただし、これらの数値は診察室での計測値を基準としており、ご自宅での家庭血圧では異なる数値が基準となります。
|
分類 |
診察室血圧(mmHg) |
家庭血圧(mmHg) |
|---|---|---|
|
収縮期血圧 拡張期血圧 |
収縮期血圧 拡張期血圧 |
|
|
正常血圧 |
<120 かつ <80 |
<115 かつ <75 |
|
正常高値血圧 |
120-129 かつ <80 |
115-124 かつ <75 |
|
高値血圧 |
130-139 かつ/または 80-89 |
125-134 かつ/または 75-84 |
|
高血圧 |
≧140 かつ/または ≧90 |
≧135 かつ/または ≧85 |
高血圧の治療
日々の血圧の測定は重要です。正確な測定を行うためには、精度の高い血圧計を使用し、毎日同じ時間に計測することが推奨されています。測定結果を記録することで、血圧の変化を把握し、適切な治療方針を立てることができます。
主に、食事療法と運動療法を通じて血圧のコントロールを目指します。食事では塩分摂取の制限やバランスの良い食事、適切な栄養摂取を心掛けましょう。また、適度な運動を継続することで血圧を改善することができます。
しかし、食事や運動の改善を行ったにも関わらず血圧が適切にコントロールされない場合、医師に相談して、薬物療法を検討することもあります。
食事療法
塩分制限
塩分の摂取過剰は血圧を上昇させる要因の一つですので、減塩は非常に重要です。特に日本人は塩分摂取量が多いとされているため、注意が必要です。日本高血圧学会では、1日の塩分摂取量を6g未満に抑えることを推奨しています。
減塩のためには、加工食品の摂取を控えることが重要です。加工食品には多く塩分が含まれているため、できるだけ加工していない食材を使用し、自身で調理することが望ましいです。また、減塩調味料や旨味調味料を上手に活用することで、食事の美味しさを損なわずに塩分摂取を減らすことができます。初めは減塩に慣れるのに時間がかかるかもしれませんが、徐々に味覚が変化し、食材本来の風味を楽しむことができるようになります。
体重制限
肥満または低体重の状態は、病気の発症リスクが高まるとされています。体格指数(BMI)は、体重を身長の二乗で割った値であり、BMI22を標準体重と定義し、BMI25以上を肥満、18.5以下を低体重とします。肥満の場合、高血圧や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病の発症リスクが増加します。
特にメタボリックシンドロームの状態では、動脈硬化を進行させ、重篤な疾患を引き起こす可能性があります。適切なカロリーコントロールを行い、適正な体重を維持することが重要です。
一方、急激な体重減少が起きた場合も、重篤な疾患の兆候となる可能性があります。特に自覚症状がなくても、若い頃に比べて大幅に体重が減少している場合は、速やかに医療機関の受診をおすすめします。
節酒
過度な飲酒は避けてください。1日に摂取するアルコールの量は、約20〜30g以下に抑えることが推奨されています。例えば、ビールの場合は500mlまでが目安です。数日ぶりに飲酒する場合でも、摂取量の上限は同じです。
禁煙
喫煙を継続すると、生活習慣の改善や薬物療法による効果が限定的であることがあります。さらに、喫煙によって末梢血管が収縮し、血圧が上昇する可能性があります。そのため、高血圧と診断された場合は、積極的に禁煙を行うことが重要です。
運動療法
 適度な運動は健康維持や病気の予防にとても重要です。運動によって血行が促進され、肥満の解消や体重管理にも効果があります。また、筋力が増すことで基礎代謝も上昇し、健康な体を維持する上で役立ちます。
適度な運動は健康維持や病気の予防にとても重要です。運動によって血行が促進され、肥満の解消や体重管理にも効果があります。また、筋力が増すことで基礎代謝も上昇し、健康な体を維持する上で役立ちます。
日常的な有酸素運動(軽いウォーキングや水泳など)を継続することをお勧めします。これによって心肺機能が向上し、体重の管理や血圧の改善に繋がります。適度な強度で長時間続けることがポイントです。
ただし、血圧が極度に高い場合や循環器疾患などの健康上の問題がある場合は、医師と相談しながら適切な運動プランを立てる必要があります。医師の指示に従い、安全かつ効果的な運動を行いましょう。
薬物療法
 患者様の状態や体質に基づいて、適切な薬を処方します。血圧を下げる薬には様々な種類があります。薬の種類によって降圧効果の程度や副作用などが異なるため、薬の処方に際しては、薬のメリットや副作用などを説明しています。患者様の理解と納得が得られるよう、十分な情報提供を心掛けています。薬物療法に関して不安な点や疑問点がありましたら、お気軽にご質問ください。
患者様の状態や体質に基づいて、適切な薬を処方します。血圧を下げる薬には様々な種類があります。薬の種類によって降圧効果の程度や副作用などが異なるため、薬の処方に際しては、薬のメリットや副作用などを説明しています。患者様の理解と納得が得られるよう、十分な情報提供を心掛けています。薬物療法に関して不安な点や疑問点がありましたら、お気軽にご質問ください。