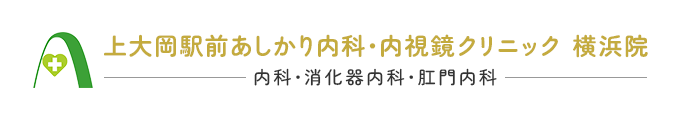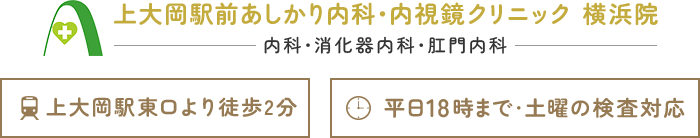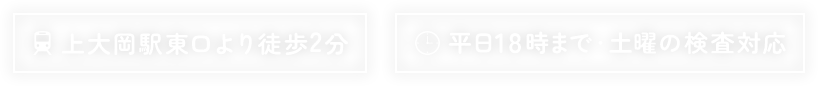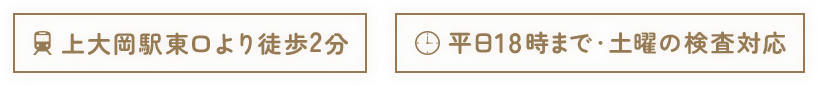【危険な下血・血便って?】
■下血・血便とは?
■危険な下血・血便とは?
■危険な下血・血便の症状と特徴
■下血・血便の色で分かる危険度
■下血・血便を伴う危険な疾患一覧
■危険な下血・血便の治療法
■下血・血便とは?
下血・血便とは、消化管(口から肛門までの消化器官)からの出血が肛門から排出される状態を指します。下血・血便には 赤い鮮血・黒っぽいタール便・血の塊が混じる便など、さまざまな種類があります。
軽度の下血・血便は、痔などの良性の疾患が原因であることが多いですが、 胃潰瘍・大腸がん・食道静脈瘤破裂 などの重篤な病気が原因で起こることもありえます。特に 大量の出血 や 黒色便、めまい、冷や汗、意識障害 を伴う場合は、緊急の治療が必要です。万が一そのような症状を確認した場合は、すぐに救急車を呼びましょう。
本ブログでは、「危険な下血・血便」について詳しく解説し、症状・原因・対処法 について詳しく紹介します。
■危険な下血・血便とは?
危険な下血・血便とは、単なる痔や軽い炎症ではなく、緊急性の高い疾患が原因となっている可能性がある下血・血便のことを指します。具体的には、短時間で大量に出血する場合や、貧血症状を伴う場合、また黒色のタール便が続く場合などが該当します。
危険な下血・血便の判断基準として、出血の色や形状が大きなポイントになります。例えば、便器の水が真っ赤になるほどの鮮血が見られる場合は、大腸憩室出血や直腸がんが疑われます。タールの黒色便が続く場合は、胃や十二指腸からの出血が疑われ、消化管の上部で出血が起こり、胃酸によって血液が黒色に変色することが原因です。
また、下血・血便に伴い、動悸やめまい、冷や汗、意識障害が見られる場合は、すでに貧血が進行している可能性があります。特に高齢者や持病を持つ方は、血圧の急激な低下を招く危険性があるため、早急な受診が必要です。
下血・血便が一度だけであれば様子を見ることも可能ですが、繰り返し発生する場合や、日を追うごとに症状が悪化している場合には、迷わず医療機関を受診するべきです。早期発見と早期治療が、命を守るための重要なポイントになります。
■危険な下血・血便の症状と特徴
危険な下血・血便の症状は、主に出血の色や状態、付随する症状によって分類することができます。
まず、鮮やかな赤色の出血が見られる場合、肛門や直腸付近で出血が発生していることが考えられます。これは痔や裂肛などの良性疾患が多いですが、大腸がんや潰瘍性大腸炎、大腸憩室出血などの重大な疾患も隠れていることがあるため注意が必要です。特に痛みがないのに赤い血が大量に出る場合は、大腸憩室出血の可能性があり、放置すると危険です。
次に、黒色のタール便が見られる場合は、上部消化管からの出血を示しており、胃潰瘍や十二指腸潰瘍、さらには胃がんや食道静脈瘤破裂などの重大な疾患が疑われます。黒色便は血液が胃酸によって変色した結果であり、時間の経過とともに腸を通過して排出されるため、便が真っ黒になるのが特徴です。このタイプの下血・血便が見られた場合は、すぐに病院で検査を受けるべきです。
また、下血・血便の他に吐血(血を吐く)や強い腹痛を伴う場合は、特に緊急性が高いと考えられます。例えば、胃潰瘍が原因で出血している場合、吐血と下血・血便が同時に発生することがあり、放置すると出血性ショックを引き起こすことがあります。さらに、動悸や冷や汗、意識がもうろうとする場合は、大量の出血により血圧が急低下している可能性があり、速やかな処置が必要です。
このように、下血・血便の色や伴う症状によって原因や緊急性が異なります。普段と違う便の色や体調不良を感じた場合は、自己判断せずに医師の診察を受けることが重要です。
■下血・血便の色で分かる危険度
下血・血便の色や形状から、出血がどの部位で起こっているのか、またどの程度の危険性があるのかを推測することができます。
|
下血・血便の色 |
考える疾患 |
危険度 |
|
鮮やかな赤色(便の表面に付着) |
痔・裂肛・直腸炎 |
低〜中 |
|
鮮やかな赤色(便に混ざる) |
大腸憩室出血・大腸がん |
中〜高 |
|
暗赤色 |
潰瘍性大腸炎・クローン病 |
中〜高 |
|
黒色(タール便) |
胃潰瘍・十二指腸潰瘍・食道静脈瘤破裂 |
高 |
鮮やかな赤い血が便の表面についている場合、肛門や直腸の炎症や裂傷による出血の可能性が高いですが、便に血が混ざっている場合は大腸の疾患の可能性があります。暗赤色の場合は大腸の奥の方や小腸の出血が疑われ、黒色便(メレナ)は上部消化管からの出血が示唆されます。
黒色便が続く場合や、大量の出血が見られる場合は、一刻も早く医療機関を受診することが必要です。出血が止まっているからといって安心するのは禁物であり、出血の原因を特定し、適切な治療を受けることが最も重要です。
■下血・血便を伴う危険な疾患一覧
下血・血便はさまざまな病気のサインとなるため、その原因となる疾患を理解することが重要です。特に危険な疾患について、代表的なものを紹介します。
①胃潰瘍・十二指腸潰瘍
胃潰瘍や十二指腸潰瘍は、薬剤やピロリ菌の影響によって胃や十二指腸の粘膜が傷つき、出血する病気です。出血が起こると、胃酸と混ざることで黒色のタール便が排出されることがあります。また、潰瘍が進行すると胃の壁が穿孔(穴が開く)することがあり、強い腹痛や吐血を伴う場合があります。
②食道静脈瘤破裂
肝硬変などが原因で門脈圧が上昇し、食道の静脈が膨らんで静脈瘤ができることがあります。これが破裂すると、大量の吐血や下血・血便を引き起こし、生命の危険にさらされることがあります。食道静脈瘤破裂は突然発症することが多く、救急処置が必要になります。
③大腸がん・直腸がん
大腸がんや直腸がんでは、がんが進行するにつれて出血することがあります。初期の段階では少量の血が便に混ざる程度ですが、進行すると下血・血便が増えたり、便秘や下痢を繰り返したりすることがあります。下血・血便が続く場合は、早期発見のために大腸内視鏡検査を受けることが推奨されます。
④潰瘍性大腸炎・クローン病
これらの炎症性腸疾患は、腸の粘膜に炎症を引き起こし、慢性的な下痢や下血・血便を伴います。特に潰瘍性大腸炎では、粘液や膿が混じった下血・血便が特徴的です。病状が悪化すると、大腸全体が炎症を起こし、大量出血や腸の破裂を引き起こすことがあります。
⑤大腸憩室出血
大腸の壁に小さな袋状の膨らみ(憩室)ができ、そこに炎症が生じたり、血管が破れることで出血が起こります。憩室出血は突然発生し、便器が真っ赤に染まるほどの大量の血便が見られることがあります。多くの場合は自然に止血しますが、出血量が多い場合は緊急治療が必要になります。
■危険な下血・血便の診断方法
下血・血便が見られた場合、病院では出血の原因や場所を特定するために、さまざまな診断方法が用いられます。どの検査を行うかは、下血・血便の色や状態、患者の症状などをもとに医師が判断します。診断が遅れると重篤な病気が進行する可能性があるため、速やかに適切な検査を受けることが重要です。
①内視鏡検査(胃カメラ・大腸カメラ)
内視鏡検査は、下血・血便の原因を特定する最も有効な方法です。消化管の内部を直接観察することで、出血部位の特定やポリープ、潰瘍、がんなどの病変を確認できます。
・胃カメラ(上部消化管内視鏡)
胃や十二指腸の状態を調べるために、口からスコープを挿入する検査です。黒色便が見られる場合、上部消化管の出血が疑われるため、胃カメラが必要になります。胃潰瘍や胃がん、食道静脈瘤破裂などが原因である可能性が考えられます。
・大腸カメラ(下部消化管内視鏡)
大腸の内部を調べるために、肛門からスコープを挿入する検査です。鮮血が混ざる便が出た場合、大腸や直腸の異常が疑われるため、大腸カメラによる精査が行われます。大腸がんやポリープ、潰瘍性大腸炎、大腸憩室出血などを診断することができます。
②血液検査
血液検査では、貧血の有無や炎症の有無を調べることができます。出血が長く続いている場合、赤血球数やヘモグロビン値が低下しており、貧血の診断に役立ちます。また、白血球数やC反応性タンパク(CRP)の値が高い場合は、感染症や炎症性疾患が関与している可能性があります。
特に、大量出血による急性貧血が疑われる場合、血液検査の結果によって輸血が必要になることもあります。
③CT検査・MRI検査
内視鏡検査では発見しにくい小腸の病変を調べるために、CTやMRIが用いられることがあります。特に、大腸カメラで出血源が見つからない場合、小腸の腫瘍や潰瘍を調べる目的で画像診断が行われることがあります。
CT検査では、造影剤を使用することで血流の異常を検出しやすくなります。MRIは詳細な画像を得るために使用されることがあり、特に腫瘍や炎症の診断に役立ちます。
④便潜血検査
便潜血検査は、肉眼では確認できない微量の血液を便の中から検出する検査です。大腸がんの早期発見に役立つため、健康診断などで広く行われています。便潜血が陽性だった場合は、大腸内視鏡検査を行い、詳しく調べることが推奨されます。
このように、下血・血便の診断には複数の検査が組み合わされることが多く、出血の状態や患者の症状に応じて適切な検査が選択されます。
■危険な下血・血便の治療法
下血・血便の治療方法は、出血の原因や重症度によって異なります。軽度の出血であれば薬物療法で対応できる場合もありますが、重度の出血では内視鏡的治療や手術が必要になることもあります。
①薬物療法
出血の原因が胃潰瘍や炎症性腸疾患の場合、薬による治療が行われます。
・胃酸を抑える薬(プロトンポンプ阻害薬など)
胃潰瘍や十二指腸潰瘍の治療に使われる薬で、胃酸の分泌を抑えることで粘膜の修復を促します。
・抗炎症薬(5-ASA製剤など)
潰瘍性大腸炎やクローン病などの炎症性腸疾患では、腸の炎症を抑える薬が用いられます。
・止血剤
軽度の出血であれば、血管を収縮させる薬を使い、出血を抑えることができます。
②内視鏡的治療
内視鏡を用いた治療は、出血部位を直接止血する方法として広く行われています。
・クリッピング(止血クリップ)
内視鏡を使って、出血している血管を金属製のクリップで止める方法です。
・電気凝固法
高周波電流を用いて出血部位を焼灼し、止血する方法です。
・硬化療法
出血している血管に薬剤を注入し、血管を硬化させることで止血を図る方法です。
③外科手術
内視鏡的治療で止血が難しい場合や、大腸がんなどの病変が原因である場合は、外科手術が必要になることがあります。
・大腸がんの手術
がんが進行している場合、腸の一部を切除する手術が行われます。
・緊急手術
大量出血が止まらず、生命の危険がある場合は、出血部位を直接縫合する手術や腸の切除手術が行われます。
このように、治療法は病気の種類や進行度によって異なります。特に緊急性の高い場合は、迅速な治療が求められます。当院では対応できない場合、即時に関係医療機関へご紹介いたします。
当院では、下血・血便の状態を丁寧に検査し、緊急性が高いのか、近い将来緊急度が高くなるのかを専門医が正確に判断いたします。ご不安な方は、まずはご相談ください。