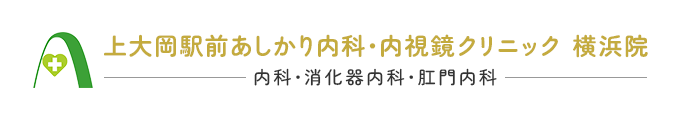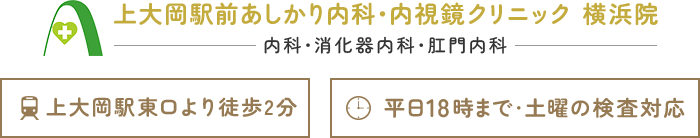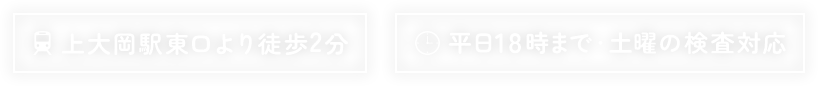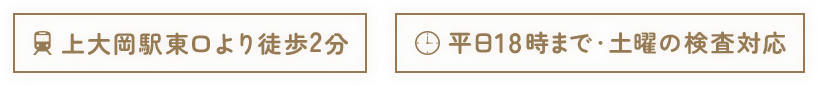食欲不振とは
 食事をする意欲が低下し、十分な栄養を摂取できない状態、また空腹感の欠如や食事内容の偏りなどを指します。
食事をする意欲が低下し、十分な栄養を摂取できない状態、また空腹感の欠如や食事内容の偏りなどを指します。
食欲不振が続くと栄養不足や体力低下などにより、日常生活に影響を及ぼす可能性があり、また疾患により食欲不振を来している場合には原疾患の特定・治療が重要です。
このようなお悩みは
ありませんか?
- 食欲が2~3週間以上も湧かない
- 食欲不振が続き体重が減った
- 食事に対して面倒くささを感じる
- 食事をするのを忘れる
- 食べたいものや食べるものが偏っている
- 食べても味がない・美味しくない
- 胃痛や腹痛があり、食欲が湧かない など
上記のような症状があってお悩みの方は、当院までお気軽にご相談ください。
食欲不振の原因
消化器などの
主な臓器疾患・状態
胃がん
胃がん細胞が分泌するサイトカインが胃の機能低下を引き起こし、食欲不振が発生することがあります。食欲不振は胃がんの初期症状としても現れることがあります。詳細は胃がんのページをご確認ください
甲状腺機能低下症
甲状腺ホルモンの分泌が低下し甲状腺機能低下症となった場合、食欲が減退し食べる量や頻度が減少します。
過度のストレス
 日常生活で過度のストレスがかかると、副交感神経の機能が抑制され、食欲が減退することがあります。ストレスによる心身の緊張状態が続くと、消化器官への血流が低下し、胃腸の運動や消化吸収が妨げられることが影響しています。
日常生活で過度のストレスがかかると、副交感神経の機能が抑制され、食欲が減退することがあります。ストレスによる心身の緊張状態が続くと、消化器官への血流が低下し、胃腸の運動や消化吸収が妨げられることが影響しています。
生活習慣の乱れ
睡眠不足、運動不足、過度の飲酒などの不規則な生活習慣は、自律神経のバランスを乱す要因となります。その結果、副交感神経の活動が抑制され、食欲が低下することがあります。
食欲不振の検査
問診
食欲不振の起きた時期や症状、体重の変化、現在服用中の薬や基礎疾患、ライフスタイルなど
*問診の情報をもとに、必要に応じて検査を行います。
内視鏡検査:胃カメラ検査、
大腸カメラ検査
 当院では、患者様の苦痛を最小限に抑えるために、鎮静剤を使用した検査を行っております。
当院では、患者様の苦痛を最小限に抑えるために、鎮静剤を使用した検査を行っております。
血液検査
甲状腺機能低下症が疑われる場合には、甲状腺ホルモンの値を確認します。
食欲不振の治療
 原因が特定された場合、それに応じた適切な治療を行います。
原因が特定された場合、それに応じた適切な治療を行います。
身体的な異常が見つからなかった場合、生活習慣の乱れや過度のストレスなど心因的な要因が考えられます。そのような場合、生活習慣の改善やストレスの解消方法などについて指導を行うことがあります。